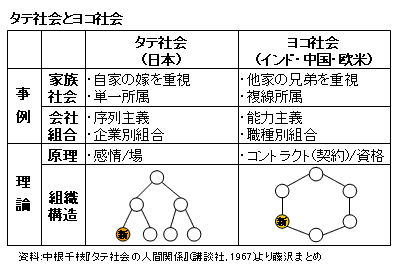第1章 自由主義はどのようにして正当化されたか
1 資本主義の正当化
★私有財産は悪であるか
・自由主義の経済的側面……私有財産と市場を基礎とする「資本主義」
・ヨーロッパ思想史の上では、私有財産と市場に対して好意的ではなかった
例:プラトンの『国家論』
・古代ヨーロッパでは、アリストテレスに見られるように、私有財産と富の蓄積については倫理的制約が課せられていた
★キリスト教世界と所有権
・古代ヨーロッパと同様の傾向は中世キリスト教世界にも見られた
新約聖書マタイ伝「富んでいる者が神の国に入るよりは、らくだが針の穴をとおる方がもっとやさしい」
トマス・アキィナス「けだしそれは、それ自身獲得欲にのみ奉仕するものであり、つねにそれ以上に拡大していく以外に限界を限界を知らないからである。それゆえ交易は、それ自身として考えられた場合、つねに一定の卑劣さを含み、それ自体としてはいかなる公正で必要な目的も含まない」
(しかし、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』によれば、ルネサンスではなく、それ自体としての営利や快楽を否定しながら、しかも救済という宗教的目的にしたがって営利を正当化しむしろ要求していったプロテスタンティズムこそが、近代資本主義を準備したとされている→カルヴァニズム)
★ジョン・ロックと私的所有の正当化
・ロックは自然状態に労働を基礎とする所有権の確立を見ていた
(1)各人は自らの身体とその諸能力の所有者である→その労働の所産も各人に帰属すべきものである(私的所有の正当化)
(2)人間にとって有用な事物の価値の99%→その生産のために費やされた労働に等しい
以上の考察より、労働の産物は各人の所有権として各人に帰属するのが正当であるとされた
★富の無限の蓄積
・最初、ロックは所有権について自然法(理性の法)による一定の制約をおいていた
・論理の過程でロックはこの制約を撤廃していく→貨幣の導入が無限の富の蓄積を可能にし、労働の余地を押し上げ、新たな生産をもたらし、社会全体の富の増大を可能とする(富の蓄積の正当化)
・しかし、貨幣の導入による生産の拡大は、所有における不均衡、不平等を産み出さざるをえない(この点の是正についてのロックの視点は少ない)
★配分の正義は交換の正義の結果である
・富、権力などの配分の基準となる正義論…アリストテレス『ニコマコス倫理学』正義は大分して2つある(「配分的正義」「整正的正義」)
・「配分的正義」とは:国家と市民との関係において成立し、各人の有する価値に応じた事物の配分を意味する(近代の算術的平等と異なる)「整正的平等」とは:市民の相互交渉において、交換された事物がその価値において相互に等しいことを要求する(ある種の階層秩序を前提とした正義概念)
・ホップズの『リヴァイアサン』では…(1)すべての個人は平等 (2)整正的正義(交換的正義)は各人の主観によって決定されるべき
→唯一の正義は契約を守ることである→事物の配分は市場を介した交換の過程に委ねられていった
・ロックもまた、法律による強制なしの自動調整メカニズムによる経済論を唱えた
★アダム・スミスと市場社会の正当化
・スミスはもはや、労働や所有権の神聖性から論を展開しようとはしなかった
・分業こそ生産力改善の最大の要因(各人が自ら特定の職業に従事することが、結果的には社会全体の富の増大につながる)
・仁愛に期待するよりも利己心に期待して働きかけた方がよい「わたしの欲しい物をください。そうすればあなたの欲しい物をあげましょう」
・資本主義の分配と交換のシステムは分配の公平さをももたらす(交換の正義が満たされる→配分の正義も満たされる)
★自然的自由の体系とユートピア資本主義
・分配と交換の正義の考え方…経済的秩序と政治的秩序の分断をもたらす(政府の介入の縮小と市場の自動調整→自然的自由の体系と呼ばれる)
・経済の論理が社会の論理となる
・資本主義のユートピア化
・しかし、自然的自由の体系は放置されれば不平等と格差を生む
第2章 社会主義の挑戦は何であったか
2 私有財産と疎外
★経済学の吸収
・マルクスが経済学の研究に着手・・・『経済学・哲学草稿』
・『経済学・哲学草稿』においてマルクスは、スミス、リカード、ジェームズ・ミル、セイ、シスモンディらの経済学(マルクスはこれらを国民経済学と呼ぶ)を積極的に吸収しつつ、彼らと異なって、私有財産を基本とする国民経済下における労働者の悲惨な状態やその諸矛盾を描き出す。
・国民経済学=私有財産という事実から出発→その諸法則を外なる法則として描きだすにとどまる→私有財産を概念的に描きだそうとしない→法則が私有財産の本質のどのような部分から発生し、人間の根本的なあり方にどのように関わっているのか問おうとしない→むしろ私有財産を所以の前提とし、疎外や諸矛盾を隠蔽。
・マルクスにとって、国民経済学批判が私有財産批判へとつながっていく。
★疎外された労働
・マルクスは『経済学・哲学草稿』において、労働による人間疎外の構造を明らかにし、私有財産を否定していく。
・第1の疎外は、労働生産物からの労働者の疎外。労働は自己実現の機会であり、労働生産物は労働者のものへとなるのが正しい。しかし、私有財産の下では労働生産物は資本家のものとなり、労働者は逆に労働生産物と疎遠となり、隷属せしめられる。
・第2の疎外は、労働過程における疎外。労働が労働生産物との疎外を意味するならば、労働者にとって労働は苦痛であり外的なものとなる。労働は労働者の成長よりは、肉体的消耗と精神的頽廃をもたらすことになる。
・第3の疎外は、類からの疎外。人間は類的存在であり、労働は肉体的欲求から自由となり、意識的なものとなるはずであった。類への参加形態の1つであったのである。しかし、労働の疎外は、類生活を単に自己の肉体的生存のための手段とし、人間本質を疎外する。
・第4の疎外は、人間の人間からの疎外。人間が相互に他の手段となり、疎遠なものとして対立的に存在せざるをえなくなる。
★私有財産の否定としての共産主義
・マルクスは人間本質を否定する私有財産を否定するのみならず、否定の否定として共産主義を掲げる。人間の活動の自己帰還として、あるいは疎外の最終的な解決として、共産主義を肯定する。
・しかしここでは、まだ歴史の過程と法則を通じて共産主義がいかに生み出されていくかについての洞察がなかった。共産主義は私有財産の否定の上に存在する理想にとどまっていた。共産主義は、まだ「科学」となっていなかったのである。
・共産主義が科学となるには、唯物史観と剰余価値という2つの発見を待ってからであった。
★唯物史観とその意味
・唯物史観が最初に具体的に示されたのは『ドイツ・イデオロギー』において。
・マルクスはそこで、出発点に置く人間は現実に生きた人間であることを強調する。
・歴史の根底にあるのは生産力と生産諸関係であり、道徳、宗教、形而上学はもちろん、政治や法律もまた上部構造としてそれらの規定のもとにある(このことなしには唯物史観は成立しない)。
★疎外論から物象化論へ
・『経済学・哲学草稿』と『ドイツ・イデオロギー』では「疎外」のニュアンスが異なる。
・『ドイツ・イデオロギー』においては、人間の社会的相関関係が、人間の意思から独立し、それ自身が一定の法則にしたがって運動しつつ、逆に人間をその中へ巻き込んでいくものとして捉えられている(人間と物との関係の転倒、人間と人間の関係が物と物との関係によって取って代わられる→疎外論から物象化論への転換)
・ここに法則科学としての経済学の成立根拠がある。
・K.ボランニーによれば、純粋な商品経済が支配的になったのは、ひとり19世紀のヨーロッパにおいてである。市場経済が社会から離床し、社会のあらゆるものが商品の価値によって支配されるようになった(道徳的世界、経済的世界、法的・政治的世界が分離しているとしたアダム・スミスの考えと異なる)。
・アダム・スミスが経済の世界に一定の自然調和的システムを見ていたのに対し、マルクスは逆に矛盾の集積による歴史変革の可能性を見ていた(矛盾と孤独の体現者である無産の大衆が既存の体制に反抗し打破していく)。