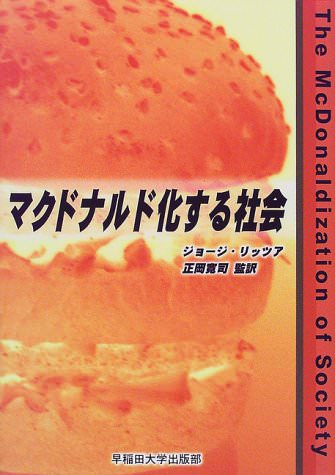言葉による世界の分断
私達は普段、言葉を使ってものごとを考えています。「今日は仕事へ行くのが面倒くさいな〜」と思うとき、「今日」「仕事」「行く」「面倒くさい」という言葉を使用して、自分の感情を認識しています。そしてこの言葉は、自分が発明したものではなく、はるか昔の人々が発明したものであり、私達はそれらの言葉を「知り」、そして「解釈して」自分のものにすることによって、はじめて言葉を使うことができます。人類にとって、言語の発明は画期的なことであったと言えると思います。言葉のない世界は「混沌」以外のなにものでもありません。「名前」をつけることができないからです。目の前を歩いている生き物に対して名前をつけることができないだけでなく、「目の前」という状況に名前をつけることができず、そもそも「生きている」という概念自体に名前をつけることもできない。そのような世界において、すべてのものは永遠に未分化なままつながっています。
言語は、私達の目の前に広がる「世界」を分断します。私達は様々な存在や状況や概念に名前をつけ、カテゴライズします。そしてこの言語による認知と分断の流れが今日の人類の発展を支えています。そう、人類の発展の歴史は、言語の発展の歴史でもあったわけです。現代、私達は様々な言葉を発明して、かつて謎に満ちていた世界(そして事象)のほとんどを、言葉によって覆い尽くそうとしています。その根幹に「名前をつける」という営為があることは言うまでもありません。
非言語あるいは未言語な存在(まだ名前がつけられていないもの。エイリアンでも未知の現象でも何でもいいです)が出現した場合にも、私達は「全身がグレーで大きな眼をした生き物」や「酸素との結合とよく似た現象」などのように、すでに存在する「名前がつけられたもの」を駆使して説明しようとします。また、よく「この気持ちは言葉にできないよ」という表現をよく耳にしますが、これもまた「この」「気持ち」「言葉」「できない」という「名前」によって説明された「言葉としての気持ち」と捉えることもできます。
言語による呪縛と言語の記号性
言語は、人類にとって永遠の呪縛です。「自分は明日から言語を廃棄する」と決意しても、それを実行することはできません。人類は発展の代償として、言語による規定を甘んじたのです。しかし、言語は私達の世界を解釈するツールとして少し力不足な面があります。
言語とは「記号」に他なりません。「今、目の前にいるノラ犬のクロを任意の点Pとするとき・・・」のように「P」とおかなくても、すでにこの言葉において「今」「目の前」「いる」「ノラ犬」「クロ」などが全部記号で表記されています。したがって、言語の使用には無意識のうちに「存在や事象のありようは記号(あるいは記号の集合体)によって代替できる」という価値判断が入り込んでいると言えます。しかし、本当に存在や事象のありようは、記号によって代替できるのでしょうか。私達は「犬」という言葉を使うことによって、どれくらい「犬」の本質に迫れているのか、むしろ本来の姿を鋳型にいれて加工したように、私達にとって都合のいいかたちで「犬」を認識しているだけではないか、という疑問がわき起こってきます。その疑問が正当なものであるか不当なものであるかを検証していく物差しは、残念ながら言語の中に内在していません。
そして言語は、「文化的なもの」でもあります。1人の人間が独自の言語を開発して1人で話し出したとしても、「頭の変な人だな」と思われるだけです。言語は、共同体の中でコミュニケーション手段として活用されていなければ意味を持ちません。したがって言語は、その共同体の文化・社会・慣習・風土などの影響と強い関係を持ちます。日本語には四季の変化を表す言葉が何百通りもあり、エスキモーには雪の白さを表す言葉が何通りもあり、ドイツ語には観念的な社会用語が沢山あります。いかなる言語であれ、それぞれの文化固有の条件に依って立っているわけです。翻訳に際しても、翻訳対象国の言語と自国語の言語が必ずしも同一関係にない場合があります。それは、単に言葉を詳しく訳して説明するだけでは理解できないニュアンスです。原文に触れてはじめて言っていることが分かったということも往々にしてあります。
解釈されたものとしての言語
さらに言語は、「解釈されたもの」でもあります。ある1つの言葉があったとして、それに対して人々が統一した意味を見いだすことは困難です。言語は意味を表現したものではないためです。たとえば、「犬」という言葉そのものには「意味」がありません。「犬」は単に対象関係をさす言葉です。「辞書」で犬の意味を引いてみても、「ネコ目イヌ科のほ乳類」という記述しか載っていません。もっとわかりやすく考えるならば、幼児期における言語学習を思い出してみるとイメージしやすいかもしれません。私達は、親や先生が絵本であるいは公園で犬を指さして、これが「いぬ」と呼ぶことを教えられました。犬の意味を直接教えてもらったわけではありません。それは、「犬」という言葉に直接の本質がないためです。
同様の例として、「愛」という言葉を考えてみましょう。「愛」を辞書で引くと、「広く、人間や生物への思いやり」と書かれてありました。そこで「思いやり」を引いてみると、「思いやること」と書かれてありました。「思いやる」を引くと、「思いをはせる」と書かれてありました。このように、私達が使っている言葉の概念は、最終的には相互の言葉の「参照関係」になっていて、それ以上の本質まで到達することはありません。したがって、言葉の本質は、「解釈」されます。同じ言葉であっても、そこから受けるイメージや、その言葉の捉え方などが人によって大きく変わってくるのはこのためです。
言語の可能性
これら言語の限界は、僕自身は中学生の時に国語辞書を開きながら考えていたのですが、いまだに自分の中でうまく解決することなく考えています。真実の追究のために言葉を駆使することが最も望ましいように見えて、実は言葉を重ねれば重ねるほど、真実とは見当はずれな方向へ行きかねないという逆説的状況。人間の理性も感性は大部分が言語によって統御され、そして理性や感性の大部分は言語によって発露するという限定状況の中で、人はいかなる可能性を言語に見いだしうるのか。
自分の言葉は、どんな「顔」をしているんだろう。